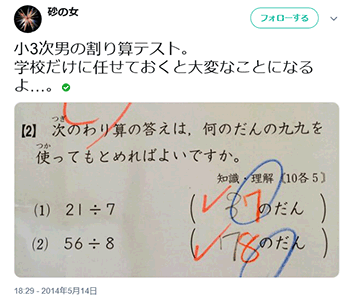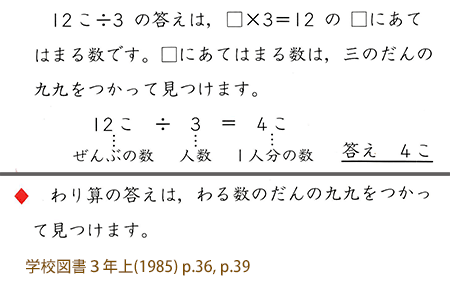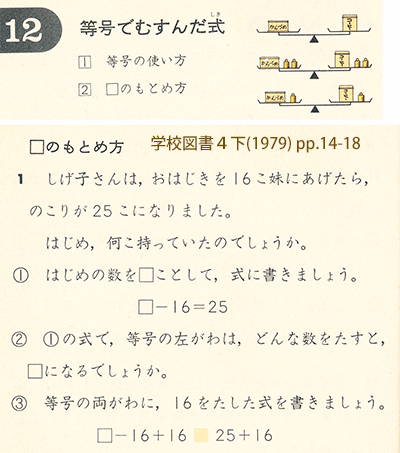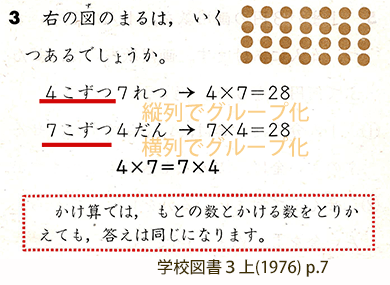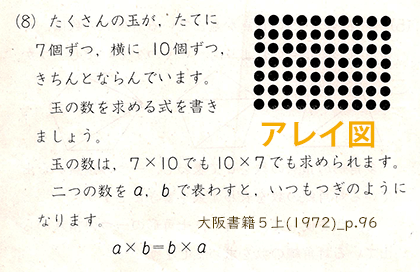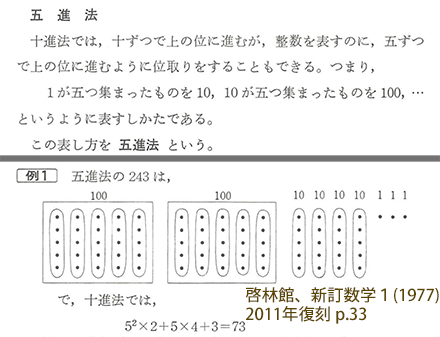(砂女氏 2014/05/14 18:29)、
2018年9月、2019年7月にも、今度は、それぞれ別の人物が、同じタイプの設問について、子どもが学校から持ち帰ったバツ採点の答案をツイッターにアップして、疑問を呈している(七氏 2018/09/08 20:50、遠藤氏 2019/07/15 08:47)。そのうち後者には、「子供がショックを受けて隠していた教育同人社の算数のテストを発見。どうみても算数教育がおかしい。」と書いている。厳しい母親から叱られるのを恐れて、100点未満の返却テスト答案を隠していたのではなく、その子自身がその設問の理不尽さにショックを受けて、答案を母親に隠していた、というのであるが、本当なのか。
3人とも、自分の子どもの解答は正解なのにバツされていると見なして、自分の子どもの答案をアップしている。つまり、子どもが「おかしな」採点をされて、トンデモ算数教育の被害を受けた、と訴えているのである。もう信頼して子どもを学校に預けられない、と言うのだ。だが、実際には、彼女らは、自分の子どもの誤解答をネットに晒してしまっているだけなのではないのか。
1.小3の割り算学習の文脈
21÷7の割り算を解くのに使う九九と言えば、3×7か7×3だが、3×7は三の段、7×3は七の段なので、三の段でも間違っていないように見えるかもしれない。この設問をそれだけで見ると、たしかに、そうであろう。だが、この設問が作られ解かれている文脈(コンテキスト)を知れば、三の段という解答が間違いであることがわかる。
割り算は小学校では3年ではじめて習う。割り算が、お菓子を子どもたちに平等に配るときに、配る人数や1人分の個数を求めるものであることが説明されたあと、割られる数が1~2桁の整数、割る数が1桁の整数の簡単な割り算を、覚えたての九九を使って、簡単に解ける方法が説明されている。
それによると、「わり算の答えは、わる数のだん九九をつかってもとめられ」るのである。21÷7 を例として使うならば、割る数の段(七の段)を、7×1=7, 7×2=14…と走査して、答えが割られる数21のところ(7×3=21)で止まり、そのときのかける数3が答えである。それに続いて、実際に、割り算を割る数の段を走査して求める練習問題がそのあとに続いている。表現は少しずつ異なるものの、どの教科書も、同様の説明・構成になっている。
注意しなければならないのは、「何の段の九九を使って求められるか」というこの設問は、わり算の答えを求めるのではなく、答えを求めるときに使う九九の段を尋ねるものだ、ということである。いわば、割り算の答えという目的そのものではなく、目的にいたるための手段を尋ねているのである。その点で、ちょっと変わった設問ではある。単元テストの他の設問が、軒並み、割り算の答えを求めるものなのに、ここだけは、割り算の答えを書いたらバツなのである。そのために、授業やドリルでやったことを忘れて、割り算の答えである3を使い、「三の段」と答えてしまう児童が少なからずいる。バツになったのなら、もう一度、教科書を読んで復習すべきであろう。
教科書には、割り算の答えは【割る数】の段で求めるとあるのだから、それがわかっているかを試す単元テストで、21÷7の例で【割る数】は7なので、七の段と答えればよいのである。同様にして、56÷8は八の段で、21÷3は三の段で、40÷5は五の段で答えを求める。
その設問の趣旨やそれが置かれた文脈からすれば、これは「割る数の段」を答える問題なのである。設問には「何の段の九九を使って求めればよいですか」とあるが、それは、言い換えれば、「授業やドリルでは、次の割り算の答えは九九の何の段を使って解くと習いましたか」という意味なのである。教科書に書かれていることををほぼ再現するだけのそのような設問は、出す価値がないように思えるが、単元テストは授業でやったことの確認なので、原則、平易で基本的な設問ばかりである。それは基礎の基礎の確認なのである。それでも、〈何の段の九九〉の設問は、目的ではなく手段を尋ねる変わった設問なので、バツになることは多い。
そのような趣旨は書かれておらず、文面だけからは、そのようなことは引き出せない、と言われるかもしれない。だが、それは授業を受けていない保護者やネットユーザーたちにとって、そうなのである。しかし実際には、この単元テストの対象者は、そのような人たちではなく、学校の授業で割り算を学習し始めた小学生である。児童は、よく授業に参加していれば、授業やドリルで同じ問題を解き、その設問の趣旨もわかっている。児童は、教師の意図や教科書の執筆者の意図を忖度する必要はない。
砂女氏は、2016年3月には、同じ画像を再掲して、次のように述べる。
「「21÷7」の答えを出すために「3×7と7×3のどちらを想起するかは自由」なのに、「7×3でもとめられる、と授業でやったからそれ以外は認めない」という採点と指導が“問題”です。」
割り算を解く方法は1つではない。割られる数から割る数を何回引けるのかと考えても、4年に習う筆算でも、電卓でも、もちろん、三の段の九九3×7を使っても、解くことはできる。わり算に限らない。2年で習うかけ算(2×3)の問題は、1年で習う足し算(2+2+2)でも解ける。他の方法があることは、わかっている。だが、すべての解法、すべての考え方を教えることはできないし、したとしても、消化不良となる。そのうち一部は、難しすぎる。だから、そのうち、その学年のその段階にふさわしい適切な解法を選んで教えるのである。
そして、その選ばれた方法を宿題や単元テストで繰り返し練習したうえで、最後に単元テストで、それが定着し、習得されているかのチェックを行うのである。答えの段を答えてしまってバツになったなら、そのバツは、他の解法の存在を否定しているのではなく、単に、「授業でやったことができていないね、復習しよう」という意味である。
2.瞬時因数分解する子どもたち
この設問について、21÷7で、三の段(3×7)でも求められる、三の段という答えは間違っていないと主張して、教師の採点を批判する者たちは、教科書を丁寧に読めば理解できる設問の趣旨を捉え損なっているだけなのではない。彼らの多くが、割り算をしているというより、瞬時に因数分解をしているらしいのである(注1)。
そのように主張する人たちは、どうも、逆引き九九が児童の頭に入っていて、児童が21を瞬間的に、3と7に因数分解するのは普通だと見なしているのである。割られる数21を因数分解すると、3×7または7×3となるが、これらが九九のどの段に属しているかと言えば、前者が三の段、後者が七の段である。もし、3×7を使ったなら、三の段でも正しいはずだ、というのである。
「数21を見ただけで数3と7が勝手に心の中に思い浮かんでしまい、続けて÷7と書かれているのを見た瞬間に答えが3だとわかってしまうような人達の存在を認識できているかどうか」(黒木氏 2014/05/20 17:20)
「総当りでもなく偶然でもなくドタマの中に「21のほうから引けるindex」が付いてるちゅうねん。除数*1から線形探索してる場合やないやろ。」(A犯氏 2017/01/14 17:51)
三の段でもよいと主張するこれらの人たちのなかには、かけ算の順序論争では自由派と呼ばれる人たちがいる。自由派の多くにとって、3×7と7×3は意味も計算結果も同じ、同一物の別の表現にすぎない。3と7が対等に同じ因数の資格で、21という積を構成しているのである。だから、21÷7という割り算を解くのに、7×3(七の段)が正しいのなら、3×7(三の段)も同じように正しいはずなのである。
だが、そうだとしたら、設問は、「その割り算の答えを求めるのに、九九のどの【句(1×1=1, 3×8=24などの、九九の1つ1つ)】を使いましたか」ときけばよいのである。ところが、「何の【段】の九九を用いましたか」と、【句】ではなく【段】を答えさせるのはなぜかといえば、7×1=7, 7×2=14, 7×3=21と, 九九のある段を走査(線形探索)することを想定しているからである。
2年生は九九を【段】ごとに習い、基本的に、掛けられる数と掛ける数から、答えを出す一方通行でのみ習う。暗唱する際に、7×1=7, 7×2=14...のように、掛ける数の小さい順に唱えるのが基本であるが、大きい順でも唱える。ときにはアトランダムでも、練習する。
たしかに、答えが18になる九九を探しましょうといった、答えから掛けられる数と掛ける数を答えさせる設問がないわけではないが、逆引きが瞬間的に出てくるまで、練習するわけではない。九九の逆引きがとくに必要となるのは、中学で多項式の因数分解のときである。だが、上記の単元テストを受けると想定されている対象者は、中3の生徒ではなく、小3になったばかりで、その前の年度にかけ算の最初の学習をはじめた小学生なのである。
たしかに、馴れてくれば、32÷4は、割る数四の段を、4×1=4, 4×2=8, 4×3=12...と、段の先頭(×1)から順に走査しなくても、あたりをつけて、4×5=20から始める児童も出てくるであろう。あるいは、段の末尾(×9)から遡及して(つまり、掛ける数の大きい順に)走査してもよい。さらに練習を積めば、最終的には、4×8に瞬時に到達するレベルに達するであろう。だが、3年の前半は、児童の大半はまだ、九九の瞬時逆引きができるレベルではない。それどころか、3年生後半になると、九九を忘れ始める児童が出るために、2年の復習が必要なのである(注2)。
小3前半というこの学習段階の児童にふさわしい割り算の方法として、割り算の筆算に先立って教えられるのが、簡単な割り算の答えを、学びたての九九を使って出すこの方法、九九の、割る数の段を走査して、答えを見つける方法、なのである。この方法に習熟することによって、児童はともかくも割り算ができる、という感覚をもつことができる。この方法は、たしかに、直接的には、桁数が少ない割り算にしか使えないものだが、同じ3年で学ぶ、あまりの出る割り算にもそのまま使える。4年で学習する割り算の筆算においても、数字の桁数が増えて複雑にはなるが、この方法と同じ発想が使われており、その意味で、この方法は割り算筆算の基礎となっている。
3.目的と手段、既知と未知
割り算をするとき、割られる数(条件1)をa、割る数(条件2)をb、割る数の段の走査(答えを得るための手段、方法)をc、答え(解、目的)をdとすると、条件と手段と目的の関係は、次のように、表現できる。
a, b ―(c)→d
割る数の段の走査に必要な条件は、割る数b、それから、2年で暗記した九九の知識である。割られる数aも最後には必要になる。割る数bは走査すべきの九九の段を与える。21÷7の例では、割る数は7なので、七の段を走査して、答えが割られる数aとなる7×3=21にまでいたる。aとbと九九の知識から、答えdが得られたのである。
もし、三の段でもいい、ということになると、その3はどこから得られたのであろうか。3はこのわり算の答えdなのである。であるから、三の段と答えた時点で、すでに、答えが出てしまっている、ということになる。三の段でもいいとする人は、ある種の「論点先取の誤謬」のようなことを犯してしまっている。答えを得るための手段として答えそのものを使ってしまう誤謬を犯している。答えが出てしまっているのなら、答えdを獲得するための手段cとしての段の走査は、そもそも不要ではないか。
三の段と答えたのでは、与えられた条件(既知)が何で、何がで問われているか(未知)、ということの理解がまったくできていないのである。この設問は、21と3という2つの数字を見たときに「想起」(砂女氏)する九九の句(7×3=2のような、九九の1つ1つ)を問うているのではない。未知の答えdを得るための手段cとしての走査する段を尋ねているのである。「割り算の答えをその答えの段を使って求める」という驚異的な不合理を何とも感じない鈍感な人だけが、三の段でも正解だと主張できるのである。
三の段でも正しいという人は、すでに述べたように、段の走査などはしておらず、1)まず3×7=21または7×3=21を思いついて、2)次に、それがどの段に属すのかを考えている。三の段でもいいと主張する人は、1)の段階で、すでに、手段の7も目的(答え)の3も得てしまっている、とも言える。つまり、手段と目的、条件と解を同時に、一体的にまず獲得してしまっている。
でも、設問は、あくまで、目的を達成するための手段、それ自身では目的ではない手段、を尋ねているのである。そこで、三の段でも正しいと主張する人は、もし3×7を思いついたのであれば、目的と手段が一体化した3と7のうち、3を目的(答え)とし、7を手段(割る数の段の走査)に、あとから割り振って、答えているのである。つまり、手段と目的を分離して、再構成しているのである。
「三の段」という誤った解答を正解に仕立て上げるために、かなり無理な事後的合理化・再構成が行われていることに注意すべきである。しかし、設問は、もともと、そのような手の込んだ解釈を、児童には要求していない。教科書に「割り算の答えは割る数の段を使って求められます」とあるので、「何の段の九九」の設問は、それに正確に対応する設問で、ただ、割る数の段(三の段)を答えればよいのである。瞬時に因数分解する方法は、大人が思いつく方法としては正当だが、やはり、小3向けのこの設問の趣旨にまったく対応していないのである。
4.あまりがある割り算
あまりがある割り算を見る前に、因数分解の仕方がもっと多い場合を考えてみよう。
瞬時因数分解する人は、たとえば、18÷3という割り算はどうするのであろうか。というのも、21を因数分解する方法は、九九の範囲では、三の段3×7と七の段7×3の2通り(または、数え方によっては1通り)しかないが、18だと、次の4通りあるからである。
1) 2×9=18 二の段
2) 3×6=18 三の段
3) 6×3=18 六の段
4) 9×2=18 九の段
だが、この場合は、1)二の段や4)九の段という答えは、不適切である。それらでは、答えの6を得ることができない。6を得るためには、3が因数に含まれている2)または3)に絞り込まれなければならない。何の段かときかれたなら、三の段ないし六の段と答えればよいことになる。だが、この絞り込みにおいて、割る数3を使っているのである。割られる数が21のときは、意識しなくてもよかったことだが、ここで、瞬時因数分解する人も、割り算の答え6を出すためには、3という割る数を使わざるをえないのである。あるいは、瞬時因数分解する同じ瞬間に、割る数3を算入しているのである。そして、答えは、割る数でないほうの因数6である。積が18で、因数が3であるときのもう1つの因数が何かを求めているのである。
だが、因数分解する人たちは、割る数3を使っているとしても、三の段を走査しているとは、依然として、言えない。そもそも、「何の段の九九を使って」と段数をきかれているのだから、何かおかしいと思わなければならない。だいたい、かけ算を被乗数×乗数ではなく、因数×因数で考える人には、段という概念がないはずなのである。
3年のうちに、小学生はあまりがある割り算も学ぶ。あまりがある割り算の答えは、どのように得るのか。これも、あまりがない割り算と同じ手法で得られるのである。
たとえば、27÷4の割り算の答えは、割る数は4なので四の段を走査する。
4×1=4, 4×2=8, 4×3=12, 4×4=16, 4×5=20, 4×6=24◯, 4×7=28×...
×7まで行ってしまうと、答えが割られる数27を超えてしまうので、1つ手前の 4×6=24まで戻る。これが停止句となる。答えが割られる数になるところで走査を停止するのではなく、答えが割られる数を超えないギリギリのところを狙うのである。このときの停止句の掛ける数8が答えであり、あまりは、割られる数27から、停止句3×8=24の答え24を引いて得られた3である。
このとき、九九の1つの段を走査しながら、いわば行きつ戻りつする。4年になって、割り算の筆算の学習が始まると、割られる数や割る数の桁数が増える。大きな数で、掛けてギリギリで超えない積を見積もる能力が求められる。あまりがある割り算での「行きつ戻りつ」の規模を拡張した形で、行きつ戻りつが必要となる。これが、足し算・引き算・かけ算になかった、割り算固有の難しさである。
では、瞬間因数分解する人は、27÷4のような、あまりがある割り算をどのように解決するのであろうか。27は3×9または9×3に因数分解できる。では、三の段ないし九の段を使うのであろうか。だが、三の段でも九の段でも、ただしい答えにたどりつけない。答えは6であり、「三の段→答え9」でも、「九の段→答え3」でもない。瞬時因数分解ではなく、4を因数の1つとする積27のもう1つの因数を求めるのだと考えたとしても、正しい答えを得られない。
正しい答えに到達するには、aが割る整数で、bがあまり(整数)、cが割られる整数であるとき、ax+b=c (b<a)となるようなxを求めることだ、と考えなければならないであろう。その場合、27÷4では、4x+b=27 (b<4)となるxとbを求める。bがゼロのとき、27は4の倍数ではないので、そのままでは、27にならない。そこで、bを1すづ増やしていく、つまり、27を1つずつ減らしていく。段の走査ではないが、ある種の走査を行うのである。26も25も4の倍数ではない(4で割り切れない)が、24ならば、4の倍数なので、因数に4を含めて因数分解できる。
24で止まり、これを4×6ないし6×4に因数分解する。4×6は四の段、6×4は六の段なので、四の段または六の段を使うということになるが、この場合も、段の走査は行っているわけではないので、「走査する段はどれか」を答えることは無意味である。4x+b=27 (b<4)を満たすxは6で、bは3である。
このように瞬時因数分解は、そのままでは、あまりがある割り算の問題を正しく解けない。ax+b=c (b<a)となるようなxを求めることだと考えても、これを瞬時にできるのであろうか。少なくとも、あまりがない割り算よりも少し時間がかかりそうだし、何と言っても、小学生にそのような方程式を解くことを期待すべきではない。小学生にふさわしいのは、やはり、割る数の段を走査する方法である。
歴史的補遺
簡単な割り算は九九を使って答える方法について、昔から教えられてきた。19世紀のリットの『新算術』(1887年)という算術書には、設問ではないが、同様の考え方が書かれている。
Nouvelle arithmétique des écoles primaires, par G. Ritt, Paris, 1887.
それによると、割る数が1位数、割られる数が2位数の簡単な割り算の商は、九九表で、簡単に求められる、という。つまり、九九表の割る数の段を水平に走査して、割られる数を見つけたら、そこから上方に遡及すると、商が発見できる。
42÷7の例では、割られる数42と割る数7か与えられ、商6を求めるのである。割る数の7の段を水平に右へと移動し、割られる数42にぶつかったところで、垂直上方に移動し、ぶつかった端にある6が商である。つまり、七の段を走査して答える。
掛け算では、被乗数と乗数が与えられ、積を求める。被乗数の7から水平に右に移動し、乗数の6から垂直に下降して、交点にあるのが積(答え)である。割り算は、掛け算との関係で言えば、被乗数と積がわかっているときに、乗数を求める演算である。
1900年の樺正董『算術教科書上』(p.45)には、次のように書かれている。この時代は、国定教科書では九九は半九九だったので、九九の段を走査するということはできなかったはずである。しかし、38÷7は、大きい順ではあるが、7に9から大きい順に掛けて、積が割られる数を割った(切った)直後で止まり、その際のもう1つの因数7が、答えとなる。段の走査ではないが、ある種の走査を行っている。
9×7=63, 8×7=56, 7×7=49, 6×7=42, 5×7=35
「1位数にてその10倍未満の数を割る場合 37. この場合は、別に法則と言うべきものはなく、ただ、乗法九九を用いてこれを被乗数に比較するまでのことである。たとえば、38を7で割るには、九九を用いて、9, 8, 7, 6, 5と7との積を38と比較すれば、38は5と7を掛けたものに3を加えたものに等しい。すなわち、商5、あまり3を得る。」
昭和初期の緑表紙教科書(1937年)にも、冒頭に掲げた「何の段の九九」型の設問が載っている(2下 p.9)。この時代には、総九九が採用されていたが、「段」という言葉は使われていない。「12÷2を計算するときには、二六12という九九を使いましょう。12÷4には、どんな九九を使いますか。※四三12」
次は、1956年の例である。ここではじめて、「段」が使われている。50÷6の答えは、六の段を走査する。「宏くんは50人を6つの班に分けるには、50÷6の計算をすればよいと考えて、六の段の九九を使って答えを探してみました。答えを7とすれば、六七42で、8あまります。」 もちろん、宏君は次の六八48まで行かなければならない。
次は1969年の教科書から。「30÷6の計算は、6×⬜=30 か ⬜×6=30の⬜に当てはまる数を見つけることです。六の段の九九を使います。」(学校図書3上 1969 p.23)
次は、1985年の例である。「割り算の答えは、割る数の段の九九を使って見つけます。」
以上のように、簡単な割り算の答えを九九を使って求める方法は、外国も含めて、古くから算数で教えられてきた。この設問を批判する砂女氏や定数氏、黒木氏、A犯氏も、割り算をこのようにして、習い始めたのである。
注
注1
「因数分解」と言えば、多項式の因数分解がまず思い浮かぶが、数の因数分解というのも存在する。自然数をこれより小さな自然数の積の形に変形することも、因数分解なのである。素因数分解はその特殊な場合と言える。英語では、とくに素数にこだわらない数の因数分解は、Wikipediaによると、"Integer factorization"と呼ばれている。この因数分解の因数を素因数(素数)に限定すると、"prime factorization"(素因数分解)となる。
注2
1939年に出版された清水甚吾『尋常小学校算術心指導書3下』には次のように書かれている。
「割り算で一番困難なところは、商の発見である。商を一挙に決定させようとすると、学級の優等児だけならそれでよいが、能力の低い児童には困難で、このため、割り算の劣等児を作ることになる。それで、最初のあいだは、割る数の段の九九を、割る数を先に呼び、小さい方から順に唱えていき、被乗数を超えたときにやめ、ひとつ少ない数を商とする。こうして経験を積むあいだに、一挙に商を発見し、あるいは、九九を大きいほうから逆に唱えた方が便利なことや、商を5として見るほうが便利なことなどを適用させるようにする。」(現代風に改めて引用した)
この引用によれば、割る数の段を走査せずとも、商を一挙に発見できる優秀な児童はいるにはいるが、並みの能力のその他大勢の児童には、それができない。だから、割る数の段を乗数が小さい方から順にたどって、対応する九九の句を発見させるのである。
練習を重ねているうちに、児童たちは、段の最初からではなく、途中から始めたり、あるいは、乗数が大きな方から段を遡ったりできるようになっていく。最終的に、あまりがない割り算で、当該の九九が瞬時に発見できるようになれば、この設問をやるようなレベルは卒業となる。
優秀な児童の能力を前提とした授業を強行するなら、割り算がわからない児童がたくさん出てしまう。これでは、義務教育終了までに、国民の算術的な能力を一定以上まで高めるという公教育の目的が果たせない。
(flute23432 2017/01/23 23:48, 2017/01/26 07:40, 2017/01/31 16:18, 2017/02/05 03:23, 2018/06/17 04:29, 2018/09/09 00:57, 2019/07/15 09:03, 2019/07/26 18:33, などのツイートに基づく)